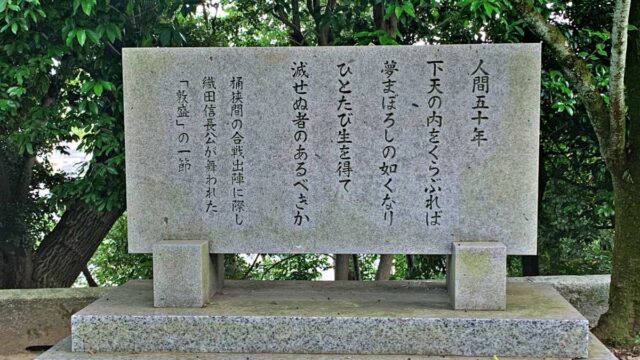 文化・教育
文化・教育 織田信長|悲しい物語「敦盛」
織田信長が好んだ「敦盛」は、一之谷の戦いで源氏方の熊谷直実が敵の大将とはいえ、当時16歳の平敦盛の首を取るといった辛い戦いを表現したものです。これには、人はそれぞれの立場で成し遂げなければならないことがある。そして人は必ず死ぬことを知り覚悟しなければならない。という両者の立場と思いが詰まっています。
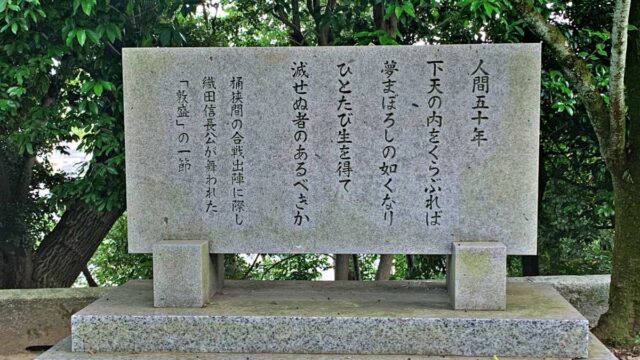 文化・教育
文化・教育  文化・教育
文化・教育  文化・教育
文化・教育  文化・教育
文化・教育  風景・観光
風景・観光  文化・教育
文化・教育  建築・インテリア
建築・インテリア  男の料理
男の料理  文化・教育
文化・教育